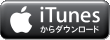正月に帰省したときに、父が一枚のCDを持ってきて言った。
「ヒカル、おいヒカル。最近ちょっといいバンドを見つけたんだ」
「なに?」
「オアシスって知ってるか?」
……オアシス今さら見つけたのかよ?
ナイツの漫才の入りみたいな話だが、実話である。
* * *
父は一年くらい前にもこんなメールをくれた。
『最近これを聴いてはまってるんだ。リンドバーグっていうバンドなんだが』
こういう還暦を僕も迎えたい、と思う。
* * *
小説でも音楽でも、およそ芸事に属するものはすべてそうだが、懐古主義は根強い。年を取ると、星の数ほどもある選択肢の中から自分の新たなお気に入りを見つけ出そうとする気力がなくなってしまうからだ。若くて気力が残っていた頃に選び取ったものだけを何年経っても褒め称え続けるようになり、結果としてオールタイムベストのリストには死人の名前がずらりと並ぶというわけだ。
60歳を過ぎても自力で音楽の大海を泳ぎ回り、オアシスやリンドバーグを見つけ出した父を見ていると、僕は少し恥ずかしくなって、実家から戻ってきてから自分のiTunesのライブラリをあらためた。21世紀のミュージシャンの曲はほとんど入っていなかった。これはまずい、と思った。
自分の中の懐古主義を焼き払うためにも今ここできっぱりと断言してしまうが、音楽は新しければ新しいほど素晴らしい。なぜって音楽という領土は有限だからだ。限られた音階、限られた有意な和声の中で、できることは18世紀と19世紀の人々がほぼやり尽くしてしまった。20世紀に生まれた音楽家たちに残された道は、石を積み上げ、塔を高く築き、重力に逆らって上へ上へとのぼっていくことだけだった。リズムを尖鋭化させ、楽器を改良し、音色を電気で加工し……多くは失敗して塔を転げ落ちていき、わずかな生き残りのための土台の染みとなる。そうした命知らずの道のりの果ての危うい高みに現代の音楽はある。昔の音楽とは踏み越えてきた屍の数がちがう。新しいものを聴き続けなければ、少なくとも音楽に関してなにか語る資格はない。
でも僕は21世紀を前にして途方にくれる。まだ10年と少ししかたっていないのに、世界はあまりにも広い。
* * *
リンキンパークを聴こうと思った理由を説明するのはものすごく難しい。いや、文章にするのはごく簡単なのだけれど、信じてもらえる自信がないのだ。しかし、正直に書こう。
僕はときおり、ある一曲を猛烈に気に入って一週間くらいリピートしっぱなしにすることがある。ほとんど病気の発作に近い。原因はよくわからないが昔からそうだった。iTunesを使うようになって各曲の再生回数が一目で較べられるようになると、これまでにその「発作」を起こしてきた曲を一覧にすることができる。
そこで僕は奇妙な共通項に気づく。曲名に同じフレーズが入っているものがいくつかあるのだ。
ひとつは"can't stop loving you"というフレーズ。マイケル・ジャクソンの"I Just Can't Stop Loving You"、TOTOの"Stop Loving You"、ヴァン・ヘイレンの"Can't Stop Lovin' You"――どれも強烈につぼにはまって100回以上聴いている曲だ。
もうひとつは"in the end"というフレーズ。ビートルズの"The End"、グリーンデイの"In the End"、つい最近仕入れたブラック・ヴェイル・ブライズの"In the End"……。
ただの偶然だろう、と自分でも思った。けれど試してみる価値はある。
僕はiTunes Storeの検索窓に"in the end"と打ち込んで、必然的に、運命的に、リンキンパークと巡り逢った。
初回の記事で僕の最愛のアーティストはクイーンだと書いてしまったが、その記述は懐古主義とともに火にくべてしまおう。なぜならiTunesの再生回数は嘘をつかない。2013年現在の僕にとって最も大切なアーティストは間違いなくリンキンパークである。In the Endを視聴した次の瞬間にはアルバムをすべて買ったし、五枚とも余さず毎日聴き続けている。僕はどれだけ好きなアーティストの曲だろうと、気に食わなければとことん聴かないたちで、クイーンですらたとえばHOT SPACEの前半の曲はiTunesに入れていなかったりするのだが、リンキンパークのアルバムはひとつも捨てるところがない。
さて、そんなわけで僕はリンキンパークを今さら見つけた。しかもそれを2013年の今になって堂々と(塙宣之のように)紹介しようとしている。冒頭の父をまったく笑えないが、アフィリエイトのためにはしょうがない。
リンキンパークはラップを織り交ぜたロックバンドだ。それ自体は21世紀では珍しくもない。そしてラップロックは僕が積極的に避けてきた音楽でもある。リンプ・ビズキットも深入りできなかったし、レッド・ホット・チリ・ペッパーズで気に入った曲もメロディアスな方面の歌ものばかりだったし、日本のものでもマキシマムザホルモンなどいくつか聴いてみたけれどやっぱりぴんとこなかった。そもそも僕はあまりラップの良さを理解できていない。なぜリンキンパークだけがここまで響いたのだろう?
理由は、今ならはっきりわかる。だれでも見ただけでわかる。彼らには、他のラップロックバンドとの決定的なちがいがある。
ヴォーカルが二人いるのである。
ラップ担当のマイク・シノダと、メロディ担当のチェスター・ベニントン。二人いるということは(たとえライヴであっても)同時に歌えるということだ。実際にリンキンパークの曲には、コーラスでチェスターが魅力的なメロディを歌い、その下でマイクがラップを刻むという形式が多い。これは僕にとっては理想的なラップの使い方だった。ラップのかっこよさとは要するに言葉の響きを使ったパーカッションなのだ(だから子音がとげとげしい英語が映えるのである)。リンキンパークはラップのその側面を極限まで追及している。象徴的なのがデビュー作HYBRID THEORYのオープニングナンバー、Papercutだ。タタタン、というキックの刻む遅めの16ビートのドラムパターンで曲は始まる。ギターが入ってイントロが盛り上がったところでマイクのラップが入ってくるのだが、単語がぎちぎちに詰め込まれ、32ビートを刻むのである。ラップを最上部パーカッションとして用いているのだ。他のどんな楽器を用いても創り出せないビートがここに生まれている。
しかしこれは理屈をこねて導き出した理由であって、僕がリンキンパークに囚われた理由の二割ほどに過ぎない。もっと根源的な理由が他にある。ヴォーカルの声の質である。
いつ気づいたのかもうよく憶えていないが、僕が好きになる男性ヴォーカルの声質には明確な傾向があった。力強いことはもちろんだが、少年的なものが含まれていることと、女性的なものが含まれていることがその条件だった。言うまでもなく理想像はフレディ・マーキュリーであり、マイケル・ジャクソンとかエリック・マーティンとかもそうだ。しかし、残念なことに少年的で女性的な声はラップに向かない。錆びていて荒削りなおとなの男の声がやはり似合う。矛盾している。どうしようもない。
だから僕が心の底から好きになれるラップロックバンドは存在し得ないはずだった。
しかし、繰り返すが、リンキンパークには、ヴォーカルが二人いる。
そうだよ。ヴォーカル二人にすればいいんだよ。その発想はなかったよ。簡単なことじゃないか。なぜ今まで気づかなかったんだろう? こんなことを言うと彼らはおそらく怒るだろう。おまえのために組んだバンドじゃねえ。ぼくのかんがえたさいきょうのラップロックバンドの話は自分のblogにでも書きやがれ。もっともな怒りだ。だからこうして自分のblogに書いている。
* * *
ところで僕がいちばん好きなのはラップがすっかりなりをひそめてしまった最新作LIVING THINGSである。
結局やっぱりラップの良さはびたいち理解できていないのかもしれない。